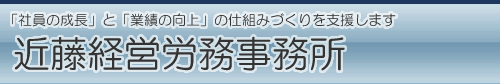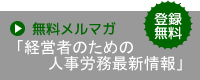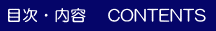1) 私的保険と公的保険

社会保険制度というのは、お金を少しづつ出し合って、それをプールしておき、病気や事故に遭った人を、そのお金で救済しようという制度です。
その社会保険制度は、大きく分けると私的保険と公的保険があります。
私的保険というのは、任意で加入する保険です。
例えば、民間の生命保険 や 損害保険 などがあります。
それから、全労済(こくみん共済)、県民共済など消費生活協同組合法に基づいて設立された共済組合があります。
この私的保険に対して、公的保険というのは強制的に加入を義務づけられている保険です。
この公的保険の中心となるものが、健康保険(介護保険を含む)、厚生年金、雇用保険、労災保険 の4つです。
その他の公的保険は、
国民健康保険、国民年金保険、船員保険、国家・地方公務員共済組合、私立学校教職員共済組合、農林漁業団体職員共済組合、後期高齢者医療制度 などがあります。
2)会社が加入する公的保険
会社が加入する公的保険は、社会保険 と 労働保険 と呼ばれるものがあります。
まず社会保険とは、厚生年金 と 健康保険(介護保険含む) のことをいいます。
この2つを合わせて、狭い意味で 社会保険 と呼んでいます。
次に労働保険とは、雇用保険 と 労災保険 のことをいいます。
この2つを合わせて 労働保険 と総称して呼んでいます。
また、この 社会保険 と 労働保険 を合わせて、広い意味で 社会保険 と呼ぶ場合もあります。
例えば、求人広告で 社会保険完備 と書いているのは、「この4つの保険にちゃんと入っていますよ」 という意味なのです。
Ⅱ 社会保険関係の手続
1)会社が事業を開始したときの手続き
従業員を雇用した場合は、社会保険と労働保険に強制加入することになります。
①健康保険 と 厚生年金 の新規加入手続を年金事務所(旧 社会保険事務所)で行います。
②雇用保険の新規加入手続を公共職業安定所(ハローワーク)で行います。
③労災保険の新規加入手続を労働基準監督署で行います。
・従業員を雇用した日から10日以内に保険関係の成立届と 労働保険の概算申告をして50日
以内に保険料の納付を行うことになります。
⇒この手続をしていない期間中の労災事故は、重大な過失とみなされるので注意が必要で
す。
④その他の手続として、次の事項は別途、労働基準監督署に届出ます。
イ.初めて従業員を雇用した場合は、適用事業報告を提出します。
ロ.従業員に残業や休日出勤をさせる場合は、時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定)
を提出します。
⇒残業をさせている会社は、従業員代表との36協定を結ぶ必要があります。
ハ.1年単位の変形労働時間制または裁量労働制などを採用した場合は、協定届を提出します。
ニ.10人以上の従業員を雇用した場合は、就業規則を作成し、従業員の意見書を添付のうえ提
出します。
2)従業員の入社に関する手続き
①従業員が入社した場合は、健康保険と厚生年金の資格取得手続を年金事務所で行います。
・入社した人によって届出書類や添付書類が異なります。
②次に、雇用保険の資格取得手続を公共職業安定所(ハローワーク)で行います。
・雇用保険は保険料が安いし、必ず加入することをお勧めします。
③労災保険は入社時の手続はありません。
・正規従業員、パート、アルバイトの区別なく、賃金を支払われる者は全て自動的に労災保険に
加入することになります。
⇒労災保険は無記名式であり、年度末に確定した1年間の賃金総額に対して労災保険料を
支払います。
3)従業員の退職に関する手続き
①従業員が退職した場合は、健康保険と厚生年金の資格喪失手続を年金事務所で行います。
・退職後も健康保険に任意で継続加入するときは、その手続も行うことになります。
⇒国民健康保険に加入する場合は、健康保険の資格喪失証明なども必要です。
②次に、雇用保険の資格喪失の手続を公共職業安定所(ハローワーク)で行います。
・資格喪失手続と同時に、失業給付(お金)を貰うのに必要な離職証明書を提出します。
⇒お金が絡むと労使のトラブルが多くなるので、離職証明書の作成には注意が必要です。
③労災保険の退職手続は何もすることがありません。
・退職後は賃金を払わないので、退職によって自動的に労災保険の対象からはずれます。
◎ 退職に伴う、雇用保険の失業給付(お金)に関してのトラブル
(事例1)
自己都合による退職の場合は、以前は6ヵ月以上の勤務実績があると失業給付(お金)を貰えましたが、現在は1年以上の勤務実績が必要になりました。
ところが、会社都合で退職する場合は、従来通り6ヵ月の勤務実績で失業給付(お金)が貰えるのです。
だから、勤務6ヵ月を超えて退職する場合は、自己都合か、会社都合なのかで揉めることが増えています。 その原因は 「退職理由の認識」 が、本人と会社で微妙に異なるからです。
(事例2)
勤続 6年で45歳の人の場合は、自己都合で退職すると90日分、会社都合で退職すると240日分の失業給付(お金)を貰えます。
勤務年数、年齢、辞めた理由によって、貰える金額が大きく変わるのでトラブルの種が一杯あります。
・トラブルを生じさせない労務管理の方法があります。 今すぐ、ご相談ください。
4)従業員の病気・けが(私傷病)に関する手続き
①病気やケガで、医師の治療を受けるときは健康保険証を使います。
・治癒するまで必要な治療を受けられ、自己負担額は3割です。
⇒自己負担額が高額になったときは、高額療養費の請求手続を行うと限度額を超えた分を払
い戻されます。
②病気やケガで仕事に就けないときは、傷病手当金を受給することもできます。
・私傷病で継続4日以上欠勤し、4日目以後の給料が出ないときに支給されます。
⇒最初の3日間は待期期間といって、その間は給付されません。
・休業1日につき標準報酬日額の3分の2が支給されます。
⇒会社から給料が一部支給されている場合は、その額を控除した額となります。
・支給開始日から1年6ヵ月以内で支給されます。
5)従業員が労災(通勤災害を含む)で医師の治療を受けるとき
①労災には健康保険証が使えません。
⇒労災では健康保険証を使ってはいけません。
・労災が起こって治療を受ける場合は、「療養の給付請求書」を病院に持参します。
⇒治癒または死亡するまで治療を受けることができます。
②労災で仕事に就けないときは、休業補償給付を受給できます。
・休業補償は、
給付基礎日額60%+休業特別支給金20%=給付基礎日額の80%が支給されます。
⇒休業4日目から療養のため休業している期間が受給できます。
③休業が1年6ヵ月を経過しても治癒していない場合は、傷病補償年金へ移行します。
・病気やケガによる障害の程度が、傷病等級に該当することが必要です。
・傷病補償年金の給付額は、
イ.傷病等級第1級 : 給付基礎日額の313日分を支給されます。
ロ.傷病等級第2級 : 給付基礎日額の277日分を支給されます。
ハ.傷病等級第3級 : 給付基礎日額の245日分を支給されます。
(その状態が継続している間支給されます)
ニ.そのほかに、傷病特別支給金も支給されます。
・第1級:114万円、 ・第2級:107万円、 ・第3級:100万円。
6)従業員が私傷病や労災で障害者になったときの手続き
①在職中の私傷病(病気やケガ)で障害となったときは、障害厚生年金を受けられます。
・その障害が1級、2級、3級に該当する限り、障害年金として一生支給されます。
⇒3級より軽い障害の場合には、障害手当金として一時金が支給されます。
②労災(業務災害および通勤災害)で障害等級表に該当する身体障害が残ったときは、傷害補償
年金を受けられます。
・第1級から第7級に該当する場合は、傷害補償年金が一生支給されます。
⇒第8級から第14級に該当する場合は、傷害補償一時金が1回限り支給されます。
7)従業員が病気やケガ(私傷病)で死亡したときの手続き
①病気やケガで死亡したときは、健康保険・厚生年金の資格喪失の手続を5日以内に行います。
・健康保険から埋葬料(本人・家族5万円)が請求により支給されます。(時効2年)
②雇用保険の資格喪失の手続を10日以内に行います。
③遺族厚生年金の受給
・遺族厚生年金を貰える遺族は、死亡した従業員と生計維持関係にあった者で、その遺族の中
で第1位の者だけに支給されます。
⇒その順位は、第1位:配偶者・子、 第2位:父母、 第3位:孫、 第4位:祖父母 の順です。
④遺族厚生年金の額
イ.年金額は、厚生年金保険に加入していた全期間の平均給与額(平均標準報酬月額)による
ので定額ではありません。 その計算方法は、短期要件と長期要件の計算方法があります。
ロ.年金額は、死亡した人が受給していた(予定だった)老齢厚生年金の4分の3の額になりま
す。
8)従業員が労災(通勤災害を含む)で死亡したときの手続き
①健康保険・厚生年金の資格喪失の手続を5日以内に行います。
②雇用保険の資格喪失の手続を10日以内に行います。
③労働基準監督署に労働者死傷病報告を提出します。
・通勤災害の場合は報告の必要がありません。
④遺族補償年金を貰える遺族は、最先順位者が年金を受給できます。
・その順位は、労働者の死亡当時、その収入によって生計を維持していた 配偶者、子、父母、
孫、祖父母、兄弟姉妹 の順となります。
⑤遺族補償年金の額は、受給権者と生計を同じくしている受給資格者の人数に応じて支給されま
す。
・遺族の人数が1人の場合は、給付基礎日額の153日分が支給されます。
・遺族の人数が2人の場合は、給付基礎日額の201日分が支給されます。
・遺族の人数が3人の場合は、給付基礎日額の223日分が支給されます。
・遺族の人数が4人以上の場合は、給付基礎日額の245日分が支給されます。
⑥遺族補償年金を受けられる者がいない場合で、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹がいる
ときは、一時金として、給付基礎日額×1000日分が支給されます。
⑦葬祭料として、次のいずれか多い額を支給されます。
・315,000円+給付基礎日額×30日分
・給付基礎日額×60日分
9)出産に関する手続き
①出産した子に関する手続き
イ.健康保険の被扶養者にする。
ロ.本人が出産のため休業し、給料が出ないときは出産手当金が支給されます。
・支給額は、休業1日当り標準報酬日額の3分の2です。
・支給される期間は、出産日以前42日+出産日後56日=合計98日分です。
ハ.本人または被扶養者である妻が出産したときは、出産育児一時金が支給されます。
・一児ごとに42万円が支給されます。
⇒H21年10月からは、出産育児一時金を出産費用に充てるよう協会けんぽから医療機
関に直接支払う仕組みに変わりましたので、まとまった費用を事前に準備する必要が
なくなりました。
・妊娠4ヵ月(妊娠85日)以上の場合は、流産でも支給対象となります。
②社会保険料(健康保険・厚生年金)免除の手続き
イ.3歳未満の子の育児休業期間中は、社会保険料の本人分と事業主分が免除されます。
ただし、この社会保険料は、届け出ないと免除されません。
ロ.免除期間中の厚生年金保険料は納付したものとみなされ、将来の年金に反映されます。
③雇用保険の育児休業給付
イ.育児休業基本給付金
・賃金月額の最大30%を受給できます。
ロ.育児休業者職場復帰給付金
・賃金月額の10%~20%を受給できます。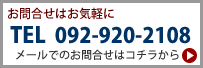
最後まで読んで頂き、ありがとうございました。 社会保険労務士 近藤 昌浩