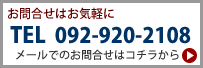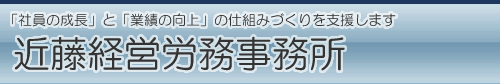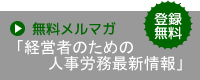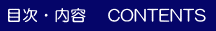作成日:2012/01/16
どんな時に賃金が増えるのか
「どんな時に賃金が増えるのか」 ということは、社員にとって大きな関心事です。
当然ながら、中小企業では年功序列型賃金制度を導入した覚えはありません。
ところが、年功序列型賃金制度だ、と思っている社員が多いのです。
その理由はこうです。
1)毎年、必ず増える賃金がある。
年齢給・勤続給
2)賃金は一度上がったら減ることはない。
降格しても、役職が外れても賃金額が変わらないという場合すらある。
この状態が長年続くと社員は勘違いというより、それが自社の賃金制度というものだと思い込んでしまいます。
そのため、賃金は必ず増えるものだとの認識しかありません。
この賃金に対する考え方を変えさせなければなりません。
・賃金は与えられるものという考え方は、×
・賃金は自ら獲得するものという考え方は、○
これは賃金に対する考え方・価値観の改革というべきものでしょう。
評価によって、賃金は増えもすれば、当然ながら減ることもある。
過去の成功体験が役に立たなくなった現在は、賃金をゼロベースで考えなくてはなりません。
昨年の賃金を今年も・来年も会社が保証することはもう有り得ません。
社員の1年間の成果により決められることとなります。
この意識改革は簡単ではありませんが、全社を挙げて、繰り返し繰り返しアナウンスされなければなりません。
質問があれば膝を突き合わせて納得されるまでじっくり説明しなければなりません。
「新賃金制度を作りました」 ということだけで済む問題ではありません。
特に説明しなければならないことは次の点です。
イ)どのような評価のとき賃金は増えるのか
ロ)どの賃金項目が増えるのか
ハ)評価によって、どのくらい賃金が増えるのか
この点が不明であると、どんな賃金制度をつくっても意味がありません。
なぜなら、これが不明なら結局 「賃金は自らの努力によって獲得するもの」 と言っても無駄であるからです。
この点、賃金の場合は明確に言えることが1つあります。
長々の説明よりも、社員がその考え方に基づいて電卓をたたくと、サッと自分で計算できる。
これが単純で一番良いのです。
来年の昇給時に評価が、
Sであれば、○○円の昇給
Aであれば、○○円の昇給
Bであれば、○○円の昇給
Cであれば、昇給なし
Dであれば、マイナス○○円
とならなければいけません。
また、次の賞与時に
Sであれば、賞与○○円
Aであれば、賞与○○円
Bであれば、賞与○○円
Cであれば、賞与○○円
Dであれば、賞与なし
と決めておかなければなりません。
事前説明がとても大切です。
賞与時になって計算するのでは遅いのです。
いや、役に立つとは言えません。
しかし、その時になってみないと個々の賞与原資がいくらあるのかだって分からないし、確定もできない、そんな意見が出るかもしれません。
もし、あなたがそう考えているのであれば、人件費総額管理をしていないということは明白です。
経営目標と人件費総額は常に連動しており、計画段階ですべて発表できるのです。
たとえば、
◎経営目標が達成できたら、賞与支給総額は昨年より○○%増額になる。
○経営目標の達成率が95%なら、賞与支給総額は昨年と同額である。
×経営目標の達成率が90%なら、賞与支給総額は昨年より5%ダウンになる。
と発表できます。
このことは、事前に発表することです。
ましてや賞与支給日に発表することではありません。
賞与支給日に発表するから、経営者が申し訳なさそうな顔をしなければならないのです。
賞与支給総額が少ないのは、経営者1人の責任ではないからです。
その理解を全社員にさせるのです。
そうしないと今の時期、強い会社にはなれません。
※社員が成長し、業績が向上する仕組づくりを支援しています。
関心がある方は、お問い合わせください。
新・人事制度研究会/近藤経営労務事務所
社会保険労務士 近藤 昌浩