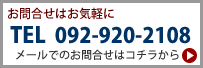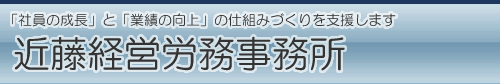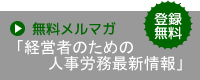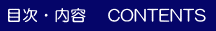今回は、その3回目です。
3つ目に問題なのは、全社員が自分の賃金額は正しいと思っていることです。
毎年、10数社の賃金制度の見直しをしていますが、誰ひとりとして 「自分の賃金額はおかしい。もらい過ぎだ」 と言った社員はいません。
では、今までの賃金の決め方は間違っていたのでしょうか。
それはありません。
経営者は毎年の昇給額を公表こそしていませんが、しっかり検討して金額を決めたのです。
それなのに、1人ひとりの賃金額と現在の成果を比較してみると、どうも一致していないのです。
そういう社員がいるのはなぜでしょうか。
それは、賃金額は積み上げ方式で加算されているからです。
それも青天井です。
どこかで、賃金そのものにストップ、またはダウンする仕組みを作っておかなければなりません。
この点で困った会社がすぐ年俸制を取り入れようとしますが、それは飛躍しすぎです。
業績評価がしっかり出来ないと上手な運用はできません。
簡単ではありません。
安易に年俸制を取り入れた会社が失敗するのは、業績評価が正しく出来ないからです。
また、年俸制を適用する社員は限定しなければなりません。
経営幹部と一部の管理者までがその対象です。
その理由は次の通りです。
私に人事制度のイロハを教えてくださった松本先生は、労働分配率が67%の会社を8年かけて37%へ改善した経験があります。
その飛躍的な改善の最大のポイントは、教育訓練についての業界の慣習を根本的に改革したことでした。
その業界の技術習得は10年かかると言われていましたが、ベテラン社員と同等の技術を、若手社員に2年間で身に付けさせる仕組みをつくることに成功したのです。
これを、賃金額で例示すると次のようになります。
〇高卒2年目のA社員(20歳)・・・・・・・・・月次賃金 22万円
(※同年代との賃金比較ではかなり良いので本人も満足している)
〇経験10年のベテランB社員(40歳)・・・・・月次賃金 35万円
(※賃金額が低いと不満がある)
A社員もB社員も同レベルの技術であり、成果もほぼ同じだとしたら、経営的にはどんな効果が出るでしょうか。
想像が付くでしょうか。
労働分配率が一気に改善するのです。
だから教育訓練は、目的を考えて体系的に実施しなければなりません。
そして、教育訓練の効果測定は必ず行う必要があります。
さて、もしこの会社が年俸制にすると、労働分配率は残念ながら改善しません。
年俸制の場合は、属人的要素を考慮せず、何らかの成果基準で年俸を決めるのでA社員とB社員の年俸は同じことになります。
A社員は大いに喜ぶでしょう。
ところが、この喜ぶ声が大きいほど新たにとても困った問題が生じます。
ベテランB社員は、若手社員に技術指導を積極的にやらなくなります。
理由は説明の必要もないでしょう。
もう一つ、経験則を説明しておきましょう。
次のAケースとBケースの場合で、社員の定着率が良くて、社員の成長が早いのはどちらでしょうか。
●Aケース (少しずつ成果に合わせて毎年昇給する)
|
|
1年 |
2年 |
3年 |
4年 |
5年 |
6年 |
7年 |
8年 |
9年 |
10年 |
|
賃金額 |
20万 |
21万 |
22万 |
23万 |
24万 |
25万 |
26万 |
27万 |
28万 |
29万 |
●Bケース (毎年の昇給額の変動が大きい)
|
|
1年 |
2年 |
3年 |
4年 |
5年 |
6年 |
7年 |
8年 |
9年 |
10年 |
|
賃金額 |
20万 |
23万 |
23万 |
24万 |
27万 |
27万 |
27万 |
28万 |
29万 |
29万 |
よく賃金制度が未整備の会社でやる失敗は、ある年に突然 「どーん」 と昇給することです。
「彼は優秀だから」 と言って、2〜3万円も一度に上げてしまうのです。
社員の立場で考えて欲しいと思います。
「今年の頑張りで3万円上がった。よし来年も頑張って同じように…」 となります。
毎年3万円で、10年で30万円の昇給。
これは絶対ありえません。
しかし、本人は誤解します。
しかも次の年は、その社員に問題があったからということで、昇給は 「0」です。
通常、社員は徐々に成長します。
それに合わせて賃金は支給されるものです。
だから、この原則をおさえてモデル賃金をつくっておくことが大事になります。
そうすると社員は、じっくりと自己育成して成長するようになります。
どの会社でも 「小才が利く」 社員が生まれるのは、そうなるような仕組みに賃金制度をつくっているからなのです。
次号に続きます。
「人事制度の仕組みづくり」 で業績向上の支援をいたします。
お気軽にご相談ください。
新・人事制度研究会/近藤経営労務事務所
社会保険労務士 近藤 昌浩