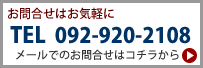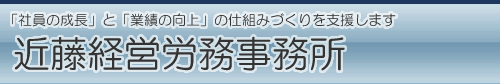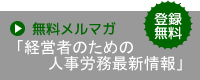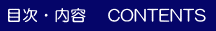A社員、B社員とも同じ能力を持っていて、昨年の実績も同じ100だったとします。
この2人の社員がそれぞれ目標設定をし、次のような実績を残しました。
○ A社員・・・目標設定130 実績120 ※ 目標達成率92.3%
○ B社員・・・目標設定110 実績110 ※ 目標達成率100%
あなたなら、どちらの社員の目標設定の仕方を選ぶでしょうか。
ほとんどの方がB社員の方を選ぶでしょう。
「社員は企業の示したゴールに向かって成長する」
この例で言えば、
「目標設定は低い方が高い評価を得られますよ」
とゴールを示していることになります。
目標管理で悩んでいる企業が異口同音で口にすることは、
「積極的にチャレンジする社員が減った」 ということです。
これは減ったのではありません。
この制度が、そういう社員を増やしたのです。
恐ろしきは、制度の間違った運用です。
それでは、人事評価シートから目標達成率を外したら、それで解決するのかと言えばそうはいきません。
会社には実現しなければならない予算があるからです。
どんなことがあっても、この予算は必達です。
そのためには、各人の目標設定は必要です。
事業年度開始の段階で予算額と目標額は一致しなければなりません。
やっぱり、社員にはチャレンジングな目標を設定してもらわなければなりません。
その前提条件として、評価と処遇が一致する制度を約束することです。
前の事例で言えば、実績額で評価するのです。
○ A社員・・・実績120
○ B社員・・・実績110
この場合は、A社員の方が高い評価になり、高い処遇が受けられることになります。
具体的には、この実績を評価する基準を事前に示すことです。
例えば、評価基準が5段階であれば次の通りです。
○ A社員・・・実績120 → 評価5
○ B社員・・・実績110 → 評価4
この評価によって、昇給や賞与が決められるのです。
この企業では、全ての社員が公平です。
不満の出る余地はありません。
もちろん、全社員と言いましたが、社員には新人もベテランもいます。
それぞれの状況で現実に近い目標を設定するでしょう。
それでも、ぐっと予算に近づくことになります。
さらに、部下の目標を高める指導にはコツがあります。
次号に続きます。
お気軽にご相談ください。
新・人事制度研究会/近藤経営労務事務所
社会保険労務士 近藤 昌浩