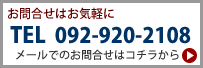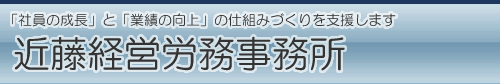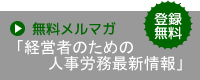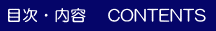管理者の昇進基準には、本人の同意ということを記載しておく必要があります。
つまり、管理者として業務を遂行するためには、過去の栄光(個人としての高業績) だけでは不充分であり、新しい管理業務に挑戦することを確認する必要があるということです。
この手続きを踏んでいないと、
「A君はダメです。何を言っても無駄ですよ。まったくやる気がないんです」。
…のような発言になります。
これは、管理者を任命する経営者の発言が大きく影響している場合が多いようです。
例えば、次のような発言をしていないでしょうか。
「君が高い成果を出したやり方を、他の社員に教えてやって欲しい」
だから、管理者は経営者に言われた通りに教えようとしました。
しかし、部下となった社員は、管理者の指導を聞き入れませんでした。
そうすると、それは部下の責任になってしまいます。
管理者は誰もが最初は誤解をします。
部下の誰もが自分の言うことを聞くだろう、指示命令に従うだろう、と思うのです。
しかしそういうことは、まずないと言った方が良いでしょう。
だからこそ、その現実を示したうえで任命するのです。
例えば、次の通りです。
管理者の部下になる社員の前回の評価結果を見せて、この評価結果を向上させることが管理者の業務であることを理解させるのです。
前回の成果がどうであり、重要業務の遂行度はどうであり、知識・技術や勤務態度がどのような状態であるかを説明するのです。
成果の低い社員は、意欲が低いことも説明します。
そして、部下を成長させたとき、つまり部下の評価結果が良くなったとき、管理者としての評価が高くなることが納得されなければなりません。
そのためにも、経営者が管理者に期待する期待像を記した 【管理職の成長シート】 は重要です。
この期待像が明確になっていれば、期待はずれとなる管理者の数も極端に減ってきます。
このプロセスを経験した会社では、管理者の部下に対する指導教育が上手になってきます。
その理由は、経営者自らが、管理者の期待像である 【管理職の成長シート】 を活用して説明し、目標を確認するからです。
そして管理者は、部下を指導する際には 【部下の成長シート】 を活用し、教育指導するようになります。
今までの場当たり的な教育指導から、計画的な教育指導に移行する際には、トップ自らが率先して実行することは大切です。
ぜひ、トップがその見本を示して欲しいと思います。
そして、その有効的な活用を工夫改善することも大事です。
この習慣が出来れば、間違っても 「ダメな管理者」 も 「ダメな社員」 もいないことが分かるでしょう。
お気軽にご相談ください。
新・人事制度研究会/近藤経営労務事務所
社会保険労務士 近藤 昌浩