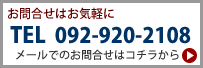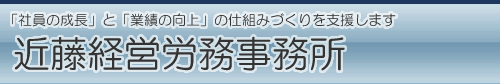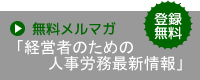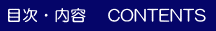その反面、上司は部下のすべてを(評価シートに掲げられていないことも含めて)観察しています。
そのため、ある出来事や、事象にとらわれてしまうことがあります。
ある特定の評価が高いと感じた場合に、別の項目の評価も高くするのです。
簡単に例えれば、ある有名大学を卒業しているからビジネスマンとして優れていると評価したり、
外国に留学して英語ができるから優れたビジネスマンだと評価する。
このような 「ハロー効果」 があることも事実です。
しかし、全体を評価するとなると左脳の仕事でなくなり、右脳の仕事になります。
右脳の仕事は、いわゆる 「勘」、つまり直感です。
残念ながら直感の評価ではうまく説明できません。
ところが、この直感はほとんどの場合正しいのです。
驚くほど当たります。
ある社長さんは言いました。
「私の直感の説明書が評価シートと考えればいいのですね」 と。
その通りです。
もちろん社長の勘による総合評価と、評価シートによる評価結果が一致しない場合は、その原因を分析して下さい。
その原因は限られています。
1.成長支援会議(評価決定会議)での成長基準(評価基準)の解釈が間違っている。
2.評価シートの成長要素(評価要素)に問題がある。
3.成長要素のウエートに間違いがある。
この原因を一つひとつ解決することにしましょう。
1.の場合は、正しい解釈を統一します。
2.の場合は、成長要素の入れ替えをします。
3.の場合は、ウエートを変更します。
そしてもう一度、仮評価を行い、結果を集計します。
その結果を確認し、「一致した!」 ということになれば、評価シートは完成です。
場合によっては、経営者の誤解もあり得ます。
非常に数は少ないですが、そんなこともあることを頭の片隅に置いておいてください。
ここまで完成すれば、安心して処遇制度(賃金制度・昇進昇格制度)へリンクできます。
〇評価の高い社員 → 高い処遇
〇評価の低い社員 → 低い処遇
処遇制度は限られた原資の配分ですから、社員の納得が得られなければ必ず不満が残ります。
部下 「私の昇給が低いと思いますが」
上司 「はい、評価を高めれば良いのですよ。そのためには…」
と、評価シートで指導します。
これが出来るか出来ないかは、組織運営の結果が雲泥の差になります。
今までは 「勘」 でやっていた処遇も、すべて説明できます。
そして誤解を恐れずに言うならば、
この仕組みなら 「やりがい」 があると信じた社員だけが定着することになります。
これは組織風土が変わるほどの出来事です。
次号に続きます。
お気軽にご相談ください。
近藤経営労務事務所
社会保険労務士 近藤 昌浩