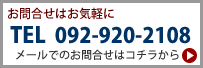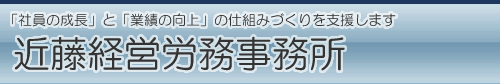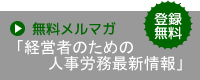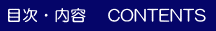「評価シートがあったら良いのに」 と経営者が思う時期があります。
それは全ての企業に共通した時期です。
そう、昇給や賞与の支給時期です。
全ての経営者は昇給や賞与の決定資料が手元にないと、その決定の正しさに不安が残るのです。
社員数が少ないときは、全ての社員の評価を自分の目で確認していましたから、「これが正しい」 と言い切れました。
人数が増えれば、一人ひとりの社員を評価する時間は少なくなり、中には評価対象期間中まったくその行動を見ていないということもあります。
この状況になったら、やはり管理者が社員を評価した評価シートの総合点数を見るしかありません。
そのために、人事上で評価シートは必要になります。
しかし、評価シートは処遇(昇給・賞与)を決めるためだけに作成するのではないのです。
評価シートをつくると経営は全く変わります。
評価シートが 「ある」 と 「ない」 とでは、組織運営が根本から変わってしまいます。
では、その評価シートがつくられ、運用されたら、どのようになるか、その様子を見てみましょう。
評価シートがあると管理者の指導が変わります。
あなたの会社では、管理者は部下にどのような教育をしていますか。
部下の成果を創出させることが管理者の期待成果です。
そのための重要業務の1つが教育指導です。
では、その重要業務を現場で具体的にはどのように行っているでしょう。
管理者 「○○君、○○しなさいよ。〇〇もやりなさいよ。そして、〇〇も…」
一方的に、やることを次々に指示命令しています。
現場でやることは沢山ありますが、それを全てやることが本当に成果を上げることになるのか疑問です。
社員にとっては、指示されたやることの全てを実行することは不可能な場合が多いのです。
1日の労働時間は8時間です。
働く時間は無限大ではありません。
そのため、すべての業務をやるということは、すべての業務を中途半端にすることと同じなのです。
この業務の取り組み方を変えてやることがポイントです。
これには 『80対20の法則』 を活用することです。
おおざっぱに言えば、「80%の成果を生む20%に注力して、20%の成果しか生まない80%を切り捨てる」 ということです。
つまり、部下の成果は、 全ての業務の中で重要業務20%の実施によって上げられているのです。
その結果が、社員間の成果の差になっています。
・優秀な社員は、
成果を上げる重要業務を完全に遂行している。
・優秀ではない社員は、
成果を上げる重要業務を全く遂行していないか、完全に遂行していない。
社員の成果の差は、この重要業務をやったかどうかの差なのです。
これを理解していない管理者は、とにかく、部下の業務で気が付いたことを注意することが自分の業務と思っています。
そして、そのやり方で一生懸命、部下を指導しています。
これでは、部下の成果を上げさせることはできません。
部下も指導されたことを実行しても、自分の成果が上がらなければ、あまり管理者の指導を受けたがらなくなります。
なぜなら、「管理者に指導されても成果が上がらない」 からです。
管理者から
・部下が言うことを聞かない
・部下が指導した通りに動かない
という発言が出たら、その管理者の指導内容が部下に役立っていない証といえます。
では、社員の評価シートが出来たら、管理者の教育指導はどのように変わるのでしょうか。
毎日、同じことを繰り返し指導することになります。
その同じことは…
社員の評価シートの中の重要業務が、5段階評価であれば、5点になるまで教育指導することです。
成果を出していない社員は、その重要業務で4点以下の評価なのです。
元来、管理(マネジメント)は重点管理です。
マネジメントの時間を1点に集中させなければならないのです。
管理者の中には、その部下の重要業務を指導していなかったという場合すらあります。
評価シートがあれば、すべての管理者が同じく評価シートの中の重要業務を一斉に教育指導するようになります。
これで、部下の成果は向上するようになります。
成果を上げることは簡単です。
成果を上げるための重要業務をやり切ることです。
それ以外にはありません。
もっとも、この重要業務を特定するときには、注意することが1つあります。
管理者は、優秀な営業社員が成果を上げている重要業務は何であるかを調査分析する必要があります。
決して、管理者が 「今の時代は〜… 」 と理想論で重要業務を決めてはいけないのです。
管理者がプレイングマネージャー(自分でも個人的に営業目標を持っている管理者)であれば、現在の活動での成功事例を持っています。
しかし、100%マネジメントになったら、現場の成功事例を自ら創出することはできません。
そのために、社員の成功事例を収集分析する能力が不可欠です。
このことを理解していないと、「昔はこうだった」 と言う管理者になってしまいます。
誰も、昔の成功事例は聞きたくありません。
それは、ほとんど自慢話にしかすぎません。
社員が知りたいのは、現在の成功事例です。
その成功事例をすべての社員に再現させることです。
そのためには、何をすれば良いのか。
その 「何を」 が重要業務です。
管理者はこの重要業務を徹底指導します。
経営者も、「今、管理者は部下に重要業務を指導している」 と分かっていますから安心して見ていられます。
間違っても 「管理者は何を指導しているんだ」 という不安や不満は発生しなくなります。
その上、管理者の指導の中で、褒めることも多くなってきます。
今までは、部下の全行動を観察し、問題点を見つけることに全神経を集中していましたが、これからは、特定の業務(仕事・行動)に指導が集中できます。
そうすると、昨日までまったく出来なかった業務が、少しでも出来るようになったら、褒められます。
最初から、褒められる状況が分かっていますから、タイミングもはずしません。
その上司から褒められるということが、部下にとって、どれだけヤル気や意欲を出させることになるか想像はつくでしょう。
そして、最初はほんの少しかもしれませんが、成果も向上しています。
こうなると、上司と部下のコミュニケーションも良くなります。
「人事制度の仕組みづくり」 で、社員の成長と業績向上の支援をいたします。
お気軽にご相談ください。
近藤経営労務事務所
社会保険労務士 近藤 昌浩