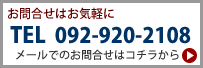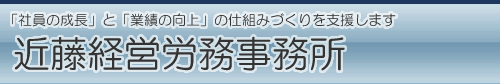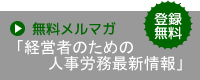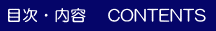経営目標を実現させるのが組織です。
組織で役割分担をするからこそ、経営目標が実現しやすくなるのです。
そのため、そのことが成長シート(評価シート)の中にも盛り込まれなければなりません。
そこで、いくつかの部門がある場合は、
管理職の成長シートには経営目標を掲げてください。
例えば、経営目標に 「売上高」 という項目があるとすれば、
○物流職の管理職の成長シート
○製造職の管理職の成長シート
○営業職の管理職の成長シート
○事務職の管理職の成長シート
のいずれにも 「売上高」 という評価要素が入っていることです。
「ええー、事務職の管理職の成長シートにもですか」
驚かないでほしいと思います。
人事部長が管理職として、役割分担したのは何故ですか。
そうです、目標売上高を達成するためです。
これは自明の理です。
社員を育てる仕組みを作ることが最終目的ではありません。
また、製造部の部長が、
「私は直接営業していないので、売上高は評価要素としては・・・」
と言っている場合ではありません。
製造部の部長が管理職としての役割分担をして、
初めて、売り上げ目標が実現できる、というこの理解が必要です。
全体責任ということではありません。
経営目標を実現するために、自部門では何をすべきなのか、
そして、
その部門の管理者は何をすべきなのか、を考えて行動しようということです。
この点を、一般職に適用できないかという発想があります。
ある顧問先企業では、
営業事務職が期待成果項目の評価要素に 「営業所全体売上高」 を入れることにより、その役割分担の意味を理解しました。
その結果は、電話応対時のアップセールという行動になりました。
また、別の顧問先から次のような質問がありました。
「会社全体の売上目標を、すべての部門の成果に入れてはダメですか?
ウエートは低い設定でも・・・」
管理職なら、「売上高」 「粗利益高」 でOKです。
但し、一般職であれば、ちょっと工夫が必要でしょう。
M会社では、製造部門、販売部門、営業部門、仕入部門、事務部門のすべての部門に 「既存顧客の継続率」 が入っています。
単純に、「売上高」 でもいいのですが、さすがに一般職の社員であると “ピン” ときません。
ピンとくるというのは、毎日仕事をしていて、
自分の仕事が、成果を上げる方向に向いているのか、そうではないのか、です。
つまり、お客様に支持されているのかどうかが具体的に分かるということです。
このように、自分たちの現場の仕事が全体成果へと、ストレートに結びついていることを分かりやすく示す指標が、御社にあると良いですね。
そこにやりがいを見出せるようにするヒントがあります。
お気軽にご相談ください。
近藤経営労務事務所/新・人事制度研究会
社会保険労務士 近藤 昌浩