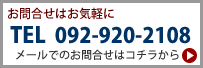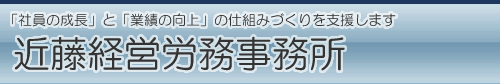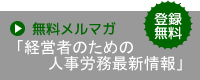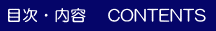人事制度における評価制度を導入し、階層別の評価シート(成長シート)を明らかにすると、ある問題が発生することがあります。
その問題を採り上げます。
階層とは、
〇一般職層
〇中堅職層(役職で言えば、主任、係長、課長補佐)
〇管理職層(役職で言えば、課長、次長、部長)
のことです。
多くの中小企業には、従業員と取締役の両方を兼ねている人が存在しますが、
この兼務取締役も評価するのかという問題があります。
この兼務取締役は、「法律上の取締役の立場」 と 「労働者の地位」 の両方を
同時に兼ねています。
例えば、
〇取締役営業部長(営業部長兼取締役)
〇取締役工場長(工場長兼取締役)
〇取締役東京支社長(東京支社長兼取締役)
といったケースです。
この場合は、明らかに労働者的な性格が存在しており、
評価シートで評価することが必要になります。
この場合の上司は誰かということですが…これは社長になります。
この評価はあくまでも、労働者としての部分の評価です。
取締役としての評価ではありません。
さらに、もう一つ問題があります。
役付取締役の評価です。
役付取締役……専務取締役、常務取締役
中小企業においては、副社長取締役もこれに含めて考えた方が良いのですが、この役付取締役は評価シートで評価する対象者になるのかということです。
一般的には、兼務取締役と違い、役付取締役に就任した場合は労働者としての身分を失うことになります。
法律的には、法人の取締役になったときには、法人との間に雇用関係はありませんので、人事制度の適用対象外になります。
ところが中小企業の場合には、役付取締役に就任しても、実態としては兼務取締役と変わらないことが多いようです。
この場合は、やはり労働者としての身分、このケースでは管理職としての部分は、しっかり評価シートで評価すべきです。
いつかは、完全に役付取締役として専任するときがくるでしょうが、それまでは評価対象者のままにしておくことです。
「専務を評価シートで評価するのはチョット…」
こういう意見があるのですが、評価するのは 「専務」 の部分ではなく、「管理職」 の部分です。
誤解の内容にしてください。
そもそも、社長、副社長、専務、常務は、法律上の用語ではありません。
実務上の用語です。
この区別をしておかないと、問題のある組織図をつくり役割分担を不明確にします。
役割分担を曖昧なままにしますと、当然評価シート(特に管理職用評価シート)がつくれません。
もっと問題なことは、組織運営上の指揮命令が混乱し、成果が出にくくなることです。
組織図を現在の実態に合わせてつくり、運営しないと組織的に機能不全になりますので、評価シートをつくる際には組織図も一緒に見直すことをお勧めします。
最後に、「部長」 「次長」 「部長代理」 「課長」 等の役職がついているが管理職の評価シートが使用できないケースについて考えます。
これは、特に営業職のように、顧客と直接面談をする必要性のある職種に顕著に発生する問題です。
通常であれば、〇〇部長とついていれば、管理職評価シートで評価することになります。
しかし、営業部長という役職名がついても、部下が1人もいないということがあります。
そのため、管理職評価シートでは合わないという質問を受けます。
この場合は、営業専門職という職種があることになります。
その職種の中でも、
ライン長としての営業部長と同等以上の組織的な役割分担をしているのであれば、営業部長として任命しても良いと考えます。
但し、ライン長としての営業部長と区別する工夫は残ります。
検討してください。
この場合は、次のような表現をお勧めします。
1つの事例としてですが…
〇営業担当部長
〇営業担当次長
〇営業担当課長
「担当」 と付けることにより、御社の組織上の位置づけを明確にすることです。
それにより、すっきりした組織運営ができます。
お気軽にご相談ください。
近藤経営労務事務所/新・人事制度研究会
社会保険労務士 近藤 昌浩