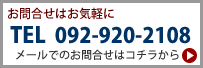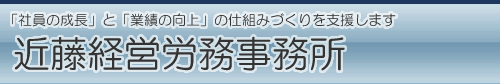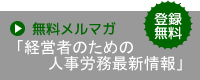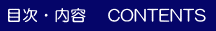作成日:2016/05/16
目標管理には2つの目的がある
経営目標が達成できない。
「かつては、こんなことはなかった」
経営環境の劇的な変化が、経営目標の達成に影響を与えています。
今までは 「前年対比110%」 くらいの経営目標であれば、そんなに実現は難しくなかったのです。
今はまったく様変わりしてしまいました。
経営者が黙っていたら、
平気で前年対比割れの目標を設定する幹部も発生する異常な事態と言えます。
すべての会社には経営目標があります。
経営計画書等に文字で表現しているかどうかは別にして、1事業年度の中で目指す目標は必ず持っています。
そのため、意識するかしないかの別はあるにしても 「目標による管理」、
つまり目標管理は実施していることになります。
一般的に目標管理は、2つの目的を持っています。
1つ目は、
目標を持つことにより、その目標が達成しやすくなるからです。
実際にこの 「人財育成・組織づくりのヒント」 を読まれている経営者の方も、
何らかの目標を持っていたからこそ、現在があることは間違いないでしょう。
経営者ご自身の体験がそれを物語っています。
そのことを自ら実証したと言ってもいいでしょう。
ところが、現在の社内を見渡すと、常に高い目標を掲げて実現しようとしている社員を見出すのはかなり難しいようです。
その傾向は、すでに幹部・管理者に伝染してしまっているとさえ思えます。
企業では、いくら経営者ひとりが高い経営目標を持ったところで、
その他の組織構成員が同じ考えで目標を掲げなければ、
全体目標は絵に描いた餅にすぎません。
常に経営者はそのことを心配しています。
いくら、必達の目標だといってトップダウンで目標を提示したところで、
社員がそれを自らの目標と心底思ってくれない限りは、心安らかにできません。
そのことを、経営者は危機感としてとらえています。
目標達成できないという危機感以前の問題です。
本気で社員自らがチャレンジ目標を設定してくれない限りは、結果は火を見るよりも明らかです。
それだけではありません。
この状況を続けたら、発展どころか存在すら厳しくなります。
経営者の頭の中は、そこまで考えを巡らせています。
一方、社員は常に環境のせいにしています。
創業関係者にとっては、もはや理解不能の世界かもしれません。
2つ目は、
目標管理することによって、人事制度を運用しやすくすることです。
特に、目標管理を評価制度に活用し、評価をより公平・公正なものにしようとするものです。
ところが、実際はどうかというと、成果項目の評価要素に 「目標達成率」 を入れようとします。
このことが定番になってから、目標設定するときの面接は上司と部下の折衝の場となってしまいました。
○部下の目標を少しでも上げようとする上司
○自分の目標を少しでも下げようとする部下
これは自然の成り行きです。
社員は評価されるように行動します。
この場合で言うのであれば、
「自分も今期は、ぜひ、目標達成率を100%以上にして上司に褒められたい」
ということです。
間違っても、
「高い目標を設定して、達成率評価を低くしたくない」
と、普通の社員なら誰でも考えつくことです。
これでは困るということで、目標設定段階での工夫もされてきました。
例えば、「目標」 に難易度を加算するということです。
分かりやすく説明すると次の通りです。
○小泉さんの目標は、前年対比110%、この難易度は120%
○安倍さんの目標は、前年対比95%、この難易度は90%
これにより、実際の目標の達成率だけではなく、それぞれ難易度を掛けるのです。
上記の例で、小泉さん ・ 安倍さん とも達成率が95% だったとします。
その場合は、評価の達成率は次の通りになります。
○小泉さん 95%×難易度120%=114%
○安倍さん 95%×難易度90%=85.5%
これでも問題はありました。
各社員の難易度を、いかに正確に決めるかということです。
ここでも各社員は、自分の目標の達成がいかに難しいか、を説得することに一生懸命になります。
以前よりもこの難易度の検討が入っただけ、問題を複雑にしたにすぎないようです。
もっと、公平に公正に評価できるように工夫改善が進んでいますが、
何か、本末転倒の動きになっています。
元来、
より高い目標を掲げて挑戦することにより、そこに成長が始まることが求められるはずでした。
逆に、評価という問題が目標管理の目的を不鮮明なものにしている感じは拭えません。
これから、この目標管理をどのように運用していったら良いのでしょうか。
ある関与先で、こんなことがありました。
社長が、
「我が社は目標の達成に関しては、幹部をはじめ、全社員が危機感を持っています」
と常々話しをされていました。
人事制度づくりが終わり、ちょうど来季の目標設定を2ヵ月後に控え、準備作業に入ったところなので、その研修をやってほしいとのことでした。
そこで、課長以上の管理者全員を集めて、目標設定研修となりました。
人事制度づくりの最中にも、競合が厳しい中でも、業績は全社目標100%を超えているという話を聞いていました。
私のイメージの中では、
相当、管理者が目標達成の指導をしていると考えていました。
そこで開口一番、
私 「K課長さん、先月の目標達成率はどのくらいですか」
K課長 「108%です」 (誇らし気に)
私 「それは素晴らしいですね。先月の目標額はどのくらいだったのですか」
K課長 「えーと…」 (即答できないのです)
これは、普段の部下との会話は目標達成率だけだったことを意味しています。
これが問題であると気がつかない方も多いのですが、とても大きな問題があります。
目標達成率は、どのくらい目標を達成しているかを示してくれますが、それ以上の情報は伝えてくれません。
それが目標額と実績額だと様々な情報を伝えてくれます。
この場合の目標は、売上高5,600万円でした。
そして、実績額は6,048万円です。
目標を超えた448万円の中身が重要です。
○どの顧客から売上げたのか。
・既存顧客と新規顧客のどちらの売上が多かったのか
○どの商品だったのか。
・ABC分析の中で、A商品か、B商品か、C商品か
○どのような売り方だったのか。
○新規商品なのか、リピート商品なのか。
: :
これが分析できない限りは、どのように行動したら成果が上がるのか、
成果の上がっていない社員への情報の共有化はできません。
目標達成率だけでしか答えられない管理者は、
部下とのコミュニケーション時の言葉も決まりきったものになりがちです。
「今月は目標を超えられそうか」
これでは、組織全体の目標を実現するための管理者の指導は不十分であることに、
早く気づく必要があります。
「人事制度」 で、社員の成長 と 業績向上 の支援をいたします。
お気軽にご相談ください。
近藤経営労務事務所
社会保険労務士 近藤 昌浩
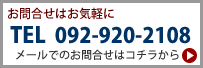
何らかの目標を持っていたからこそ、現在があることは間違いないでしょう。
経営者ご自身の体験がそれを物語っています。
そのことを自ら実証したと言ってもいいでしょう。
ところが、現在の社内を見渡すと、常に高い目標を掲げて実現しようとしている社員を見出すのはかなり難しいようです。
その傾向は、すでに幹部・管理者に伝染してしまっているとさえ思えます。
企業では、いくら経営者ひとりが高い経営目標を持ったところで、
その他の組織構成員が同じ考えで目標を掲げなければ、
全体目標は絵に描いた餅にすぎません。
常に経営者はそのことを心配しています。
いくら、必達の目標だといってトップダウンで目標を提示したところで、
社員がそれを自らの目標と心底思ってくれない限りは、心安らかにできません。
そのことを、経営者は危機感としてとらえています。
目標達成できないという危機感以前の問題です。
本気で社員自らがチャレンジ目標を設定してくれない限りは、結果は火を見るよりも明らかです。
それだけではありません。
この状況を続けたら、発展どころか存在すら厳しくなります。
経営者の頭の中は、そこまで考えを巡らせています。
一方、社員は常に環境のせいにしています。
創業関係者にとっては、もはや理解不能の世界かもしれません。
2つ目は、
目標管理することによって、人事制度を運用しやすくすることです。
特に、目標管理を評価制度に活用し、評価をより公平・公正なものにしようとするものです。
ところが、実際はどうかというと、成果項目の評価要素に 「目標達成率」 を入れようとします。
このことが定番になってから、目標設定するときの面接は上司と部下の折衝の場となってしまいました。
○部下の目標を少しでも上げようとする上司
○自分の目標を少しでも下げようとする部下
これは自然の成り行きです。
社員は評価されるように行動します。
この場合で言うのであれば、
「自分も今期は、ぜひ、目標達成率を100%以上にして上司に褒められたい」
ということです。
間違っても、
「高い目標を設定して、達成率評価を低くしたくない」
と、普通の社員なら誰でも考えつくことです。
これでは困るということで、目標設定段階での工夫もされてきました。
例えば、「目標」 に難易度を加算するということです。
分かりやすく説明すると次の通りです。
○小泉さんの目標は、前年対比110%、この難易度は120%
○安倍さんの目標は、前年対比95%、この難易度は90%
これにより、実際の目標の達成率だけではなく、それぞれ難易度を掛けるのです。
上記の例で、小泉さん ・ 安倍さん とも達成率が95% だったとします。
その場合は、評価の達成率は次の通りになります。
○小泉さん 95%×難易度120%=114%
○安倍さん 95%×難易度90%=85.5%
これでも問題はありました。
各社員の難易度を、いかに正確に決めるかということです。
ここでも各社員は、自分の目標の達成がいかに難しいか、を説得することに一生懸命になります。
以前よりもこの難易度の検討が入っただけ、問題を複雑にしたにすぎないようです。
もっと、公平に公正に評価できるように工夫改善が進んでいますが、
何か、本末転倒の動きになっています。
元来、
より高い目標を掲げて挑戦することにより、そこに成長が始まることが求められるはずでした。
逆に、評価という問題が目標管理の目的を不鮮明なものにしている感じは拭えません。
これから、この目標管理をどのように運用していったら良いのでしょうか。
ある関与先で、こんなことがありました。
社長が、
「我が社は目標の達成に関しては、幹部をはじめ、全社員が危機感を持っています」
と常々話しをされていました。
人事制度づくりが終わり、ちょうど来季の目標設定を2ヵ月後に控え、準備作業に入ったところなので、その研修をやってほしいとのことでした。
そこで、課長以上の管理者全員を集めて、目標設定研修となりました。
人事制度づくりの最中にも、競合が厳しい中でも、業績は全社目標100%を超えているという話を聞いていました。
私のイメージの中では、
相当、管理者が目標達成の指導をしていると考えていました。
そこで開口一番、
私 「K課長さん、先月の目標達成率はどのくらいですか」
K課長 「108%です」 (誇らし気に)
私 「それは素晴らしいですね。先月の目標額はどのくらいだったのですか」
K課長 「えーと…」 (即答できないのです)
これは、普段の部下との会話は目標達成率だけだったことを意味しています。
これが問題であると気がつかない方も多いのですが、とても大きな問題があります。
目標達成率は、どのくらい目標を達成しているかを示してくれますが、それ以上の情報は伝えてくれません。
それが目標額と実績額だと様々な情報を伝えてくれます。
この場合の目標は、売上高5,600万円でした。
そして、実績額は6,048万円です。
目標を超えた448万円の中身が重要です。
○どの顧客から売上げたのか。
・既存顧客と新規顧客のどちらの売上が多かったのか
○どの商品だったのか。
・ABC分析の中で、A商品か、B商品か、C商品か
○どのような売り方だったのか。
○新規商品なのか、リピート商品なのか。
: :
これが分析できない限りは、どのように行動したら成果が上がるのか、
成果の上がっていない社員への情報の共有化はできません。
目標達成率だけでしか答えられない管理者は、
部下とのコミュニケーション時の言葉も決まりきったものになりがちです。
「今月は目標を超えられそうか」
これでは、組織全体の目標を実現するための管理者の指導は不十分であることに、
早く気づく必要があります。
「人事制度」 で、社員の成長 と 業績向上 の支援をいたします。
お気軽にご相談ください。
近藤経営労務事務所
社会保険労務士 近藤 昌浩