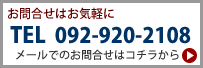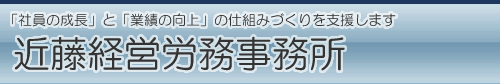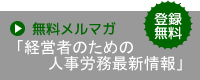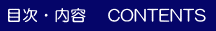外発的動機づけは、外側から動機づけるということです。
例えば、地獄の特訓的なものから、スパルタ的な研修まであります。
これらの研修を受けると、感動も意欲も湧いてきます。
その学びの深さは人により大きな個人差があります。
このような研修は確かに大切な研修です。
しかし、その感動や意欲も時が経つにつれ、
過去のものとなっていく人が多くいるのも事実です。
管理者研修のテーマも、この動機づけの部分に大きな時間を割きます。
管理者とは、部下を育てて成果を出す人ですから、
特に動機づけができるかどうかが組織の成果を左右することになります。
「どうしたら、部下にやる気を持たせることができるか」
この悩みは管理者にとっては常に頭から離れません。
人材開発技法のコーチングというものもそのことに注力します。
コーチングの場合は上から一方的にやらせるというより、エデュケーション、
つまり、その社員の能力・可能性を引き出すことを特徴としています。
何か今の時代に適合した方法のように感じます。
ところが、このコーチングも役に立たない社員がいるのです。
社員が心を開いて、聞く耳を持たなければ、何も受け入れることはありません。
いくら愛情を持って指導しても無意味なのです。
まずは聞く耳を持つようにしなければなりません。
このことに思い当たることはありませんか?
あなたはいつも学ぶことに貪欲で、
セミナーや研修会、CD・DVDによる録音・映像や書籍など、
手当たり次第に勉強されたことでしょう。
それはあなたが学ぶ姿勢を持ち、聞く耳を持っているからです。
しかし、あなたが学ばせたいと思っている社員に研修への参加や、
役に立つと考えている書籍を渡したときに喜んだでしょうか。
中には嫌な顔をする社員もいたでしょう。
それは、心の耳がふさがっているのです。
この社員は、最初からコーチングを受けようとはしていません。
コーチングを指導している方々も、その具体的な方法を持っていません。
コーチングスキルの中にもその方法が確立していないのです。
自分が自らを動機づけることを内発的動機づけといいます。
そうです。
心の中から、自分でやる気がふつふつと湧いてくる状態を作ることです。
その状態をつくるには、ハーツバーグの動機づけ要因が役に立ちます。
その動機づけ要因のトップ3は、
〇達成感
〇承認
〇仕事そのもの
です。
この中で、トップの 「達成感」 は最も有効な動機づけになります。
次の 「承認」 とは対になります。
具体的に説明すると、次の通りです。
「A社員がある目標を達成しました。
本人はその充実感を味わい満足しています。
よーし、次は〇〇を目指そうと、心に思っています」
ちょうどそのときに、上司が一声かけました。
『A君、良くやったね。 素晴らしいよ。
君ならできると思っていたよ。 さすがだね。
これからも期待しているよ』
益々、A社員の意欲は高まっていきました。
ポイントは2つです。
◎ 1つは、本人が達成感を味わう
◎ 次は、上司がほめる(その実績を認める)
これがあれば、社員は内発的な動機づけができます。
とても簡単です。
すぐに今日からでも実行されてみてください。
お気軽にご相談ください。
近藤経営労務事務所
社会保険労務士 近藤 昌浩