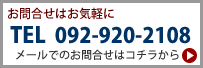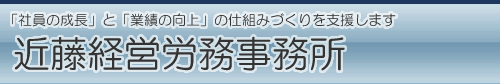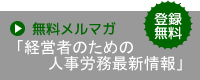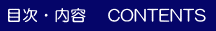プロセス指標のデータは、本人にとっては自己育成のバロメータです。
そのデータを見ながら自分の重要業務のやり方が改善されたことを振り返ることになります。
その過程で、上司は指導アドバイスするデータにもなるのです。
プロセス指標 = 行動指標 = 改善指標 = 指導指標
ところが、このプロセス指標を結果指標として使っている会社があるようです。
「〇〇〇(プロセス指標)が向上しないぞ。どうしたんだ!」
「ああー、これでは達成管理は失敗する」(涙)
プロセス指標を結果管理に使った会社の末路は見えています。
プロセス指標のデータ不正申告です。
つまり、嘘の申告です。
ある事例を紹介します。
≪ある製造会社の工場≫
製造業では、不良品を出さないことが事業目標として掲げられます。
しばしば言われることですが、営業社員はこの不良品から発生するクレーム処理に相当な時間を割いています。
このクレーム処理と納期確認が営業社員の労働時間のほとんどを占め、本来の営業活動ができない会社もあります。
そこで、この会社はポカミス回数をプロセス指標にしました。
製造現場でのポカミス回数が減れば、不良品は発生しません。
これをハインリッヒの法則(ヒヤリ・ハットの法則)で説明します。
法則名はこの法則を導き出したハーバート・ウィリアム・ハインリッヒに由来しています。
その彼が労働災害の発生確率を分析したものです。
この法則によると、1件の重大災害の裏には29件のかすり傷程度の軽災害があり、
その裏には怪我はしないがヒヤッとした300件の体験があるというものです。
これをビジネスにおいても活用しています。
例えば、300件の小さな失敗(外部からの苦情にはなっていない)があると、
29件の顧客からのクレームが発生し、1件の大失敗を生み出すのです。
この会社は、年間のクレーム件数が10件ありました。
これは工場長も呼び出されるくらいの重大な失敗です。
ここから推測すると、顧客からの苦情が10件×29倍=290件、
そして工場内の小さなポカミスが10件×300倍=3000件あることになります。
このポカミスを発生させないようにしない限りは、
この重大なクレーム10件を減らすことはできません。
理論上の計算ですが、このポカミスを年間299件以下に抑えることができたら、
重大なクレームは0件になります。
この会社の場合、このポカミスを報告する仕組みはありませんでした。
そのため、クレームが発生するたびにその担当者が呼ばれて厳重注意を受けます。
○不良品を入れない
○不良品を作らない
○不良品を出荷しない
ほとんど毎回、方向性の確認をすることで終始しています。
そこで、このポカミスを報告してもらうことにしたのです。
○品質上のポカミス
○作業場のポカミス
○怪我(どんな小さなものでも)
このポカミスが明確になり、
その発生を防ぐ解決策が打たれない限りは重大クレームはゼロにはなりません。
当初、この会社の社員はこのポカミス回数を報告するのをためらっていました。
「ポカミス回数が多かったら叱られる。その上、評価も悪く、処遇も悪くなる」
そこで、その会社の社長、役員と話し合い、ある了解を取り付け、全社員の前で
次のような説明をしました。
「ポカミスがあっていいじゃないですか。 ポカミスしようと思ってミスをした人は
誰もいま せん。 ここにいるベテランの社員さんも、若いころは随分と失敗を
したでしょう。(笑い)」
「しかし、上司から指導を受けたり、自己育成して、そのミスを減らしていきました。
だから現在のベテラン社員になったのです。 失敗せずにベテランになった方が
いたら、手を挙げてください。(シーン)」
「問題はここからです。 そのポカミスをどのように減らしていくかです。 そのため
には、自分の 工夫改善のアイディアも必要でしょう。 しかし、もっと有効なのは
上司やベテランの指導・アドバイスだと思いませんか。 この小さな失敗を一刻も
早く無くしたい社員のために明日よりポカミス回数を報告してもらいます。 推測
によると、毎日13件の ポカミスが発生しています」
「これを毎日、皆さんに報告してもらい、対策を毎日考えることにしたいのです。
そのために、各現場の責任者の方々にお願いがあります。 ポカミス回数の報告
が あっても怒らないでください。 これは、報・連・相です。 皆さんがいつも言って
いる部下の問題を報告することです。 その都度、ご指導をお願いします」
その場では、全管理者が 「ウンウン」 と、うなづき納得してくれたようでした。
その後、その会社から毎週報告を受けていましたが、そのポカミス回数が1ヵ月
で急激に減っているのです。
そこで、その点を工場長に確認しました。
「今までのポカミスを減らすために、どのような仕組みができましたか?」
「まだそこまで、できていません」
日々、ポカミスの急激な減少は、
その解決策としての仕組みによってしか実現しないものだし、継続しないものです。
そこで、その工場の社員に名前を明かさないことを条件に実態を調べました。
その社員は小さな声で言いました。
「毎日のポカミスが減らないので、作業長(上司)が 『どうしてうちの所だけ、
こんなにポカミスが多いんだ』 って、怒鳴るんです。 私は辛くて、意図的に
回数を減らしています」
この作業長は、
「みんなも本気で作業に取り組んでくれている」 と、喜んでいるかもしれません。
しかし、作業現場の年間3000件の小さなミスが無くならない限り、
10件の重大クレームは発生することになるのです。
「わかりました。現場の小さな失敗を隠さなくていいようにしましょう」
「でも、本心を言うと、その小さな失敗も早くゼロにしたいですね」
これも極論から言うと、不可能ではありません。
それは同じ商品を同じマーケットに対して、同じ社員で同じ作り方をすれば可能です。
でも、これは事業がライフサイクルの成熟期に入ったことを意味します。
その次は衰退期です。
成熟期に入って、小さな失敗がなくなって良かったとは言えないでしょう。
本末転倒ですから。
○新しい商品
○新しいマーケット
○新しい社員
○新しい作り方
に挑戦し、社会に貢献するのが使命であるとすれば、
やはり小さな失敗は生まれてしまいます。
この小さな失敗をダイヤモンドの原石として扱うかどうかが
企業の成長力を左右する大きな要因となることでしょう。
「人事制度」 で、社員の成長 と 業績向上 の支援をいたします。
お気軽にご相談ください。
近藤経営労務事務所
社会保険労務士・人事コンサルタント 近藤 昌浩