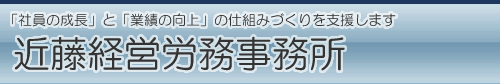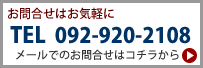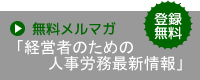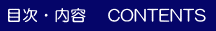従業員から、親の介護のために、介護休業を取得したいという相談があった。介護休業を取得した従業員はまだいないため、社労士に相談することにした。

先日、従業員から親の介護のために介護休業を取得したいという相談がありました。詳しい状況は今後確認することになりますが、そもそもどのような場合に介護休業が取得できるのか等、教えてください。

わかりました。具体的な取り扱いは、就業規則(育児・介護休業規程等)を確認していただくことになりますが、御社では法令通りの基準となっていたかと思います。介護休業の取得については、まず(1)従業員が介護休業を取得できる対象者であるか、(2)介護が必要な家族が対象家族の範囲に該当しているか、そして(3)その対象家族が要介護状態であるかの3点を確認する必要があります。

相談があったのは、勤続10年目の正社員です。

なるほど、それであれば介護休業を取得できる従業員ですね。念のために介護休業を取得できる雇用期間の要件を確認しておくと、契約社員のように有期雇用の場合には、介護休業開始予定日から起算して、93日経過日から6ヶ月を経過する日までに契約が満了することが明らかであるときは、取得できないとすることができます。また、労使協定の締結があれば、有期雇用・無期雇用に関わらず継続して雇用された期間が1年に満たない従業員は、介護休業の申し出を拒むことができるとされています。今回の従業員はこれらに該当しないため、介護休業が取得できます。

一度、労使協定を確認する必要がありますね。今後は申し出のあった従業員の雇用形態と勤続年数をまずはチェックすることにします。

さて、「介護が必要な家族が対象家族の範囲に該当しているか」という点ですが、今回は親の介護ですので対象家族に該当します。対象家族とは、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫になります。そして、その対象家族が要介護状態にあるということがポイントとなります。

要介護状態とは、介護保険制度で要介護状態に該当している必要があるのですよね?
そのように誤解されている方が多いのですが、育児・介護休業法に定める要介護状態とは、「負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態」のことをいいます。この常時介護を必要とする状態について、厚生労働省から「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」が示されていますので、この基準に従って判断することになります。

判断基準があるのですね。

はい。その判断基準ですが、実は2025年4月より見直しされることになっています。現行の判断基準は、主に高齢者介護を念頭に作成されており、子どもに障害のある場合や医療的ケアを必要とする場合には解釈が難しいケースも考えられるということで、見直しが行われています。

介護休業はそのような場合にも取得できるのですね。

2025年4月からの判断基準をみておくと、常時介護を必要とする状態とは、以下の1.または2.のいずれかに該当する場合であることとされています。
- 表の項目(1)〜(12)のうち、状態について2が2つ以上または3が1つ以上該当し、かつ、その状態が継続すると認められること。
- 介護保険制度の要介護状態区分において要介護2以上であること。
| 項目 \ 状態 | 1(注1) | 2(注2) | 3 |
| (1)座位保持(10分間一人で座っていることができる) | 自分で可 | 支えてもらえればできる(注3) | できない |
| (2)歩行(立ち止まらず、座り込まずに5m程度歩くことができる) | つかまらないでできる | 何かにつかまればできる | できない |
| (3)移乗(ベッドと車いす、車いすと便座の間を移るなどの乗り移りの動作) | 自分で可 | 一部介助、見守り等が必要 | 全面的介助が必要 |
| (4)水分・食事摂取(注4) | 自分で可 | 一部介助、見守り等が必要 | 全面的介助が必要 |
| (5)排泄 | 自分で可 | 一部介助、見守り等が必要 | 全面的介助が必要 |
| (6)衣類の着脱 | 自分で可 | 一部介助、見守り等が必要 | 全面的介助が必要 |
| (7)意思の伝達 | できる | ときどきできない | できない |
| (8)外出すると戻れないことや、危険回避ができないことがある(注5) | ない | ときどきある | ほとんど毎回ある |
| (9)物を壊したり衣類を破くことがある | ない | ときどきある | ほとんど毎日ある(注6) |
| (10) 周囲の者が何らかの対応をとらなければならないほどの物忘れなど日常生活に支障を来すほどの認知・行動上の課題がある(注7) | ない | ときどきある | ほとんど毎日ある |
| (11)医薬品又は医療機器の使用・管理 | 自分で可 | 一部介助、見守り等が必要 | 全面的介助が必要 |
| (12)日常の意思決定(注8) | できる | 本人に関する重要な意思決定はできない(注9) | ほとんどできない |
(注1)各項目の1の状態中、「自分で可」には、福祉用具を使ったり、自分の手で支えて自分でできる場合も含む。
(注2)各項目の2の状態中、「見守り等」とは、常時の付き添いの必要がある「見守り」や、認知症高齢者、障害児・者の場合に必要な行為の「確認」、「指示」、「声かけ」等のことである。
(注3)「(1)座位保持」の「支えてもらえればできる」には背もたれがあれば一人で座っていることができる場合も含む。
(注4)「(4)水分・食事摂取」の「見守り等」には動作を見守ることや、摂取する量の過小・過多の判断を支援する声かけを含む。
(注5)「危険回避ができない」とは、発達障害等を含む精神障害、知的障害などにより危険の認識に欠けることがある障害児・者が、自発的に危険を回避することができず、見守り等を要する状態をいう。
(注6)(9)3の状態(「物を壊したり衣類を破くことがほとんど毎日ある」)には「自分や他人を傷つけることがときどきある」状態を含む。
(注7)「(10)認知・行動上の課題」とは、例えば、急な予定の変更や環境の変化が極端に苦手な障害児・者が、周囲のサポートがなければ日常生活に支障を来す状況(混乱・パニック等や激しいこだわりを持つ場合等)をいう。
(注8)「(12)日常の意思決定」とは、毎日の暮らしにおける活動に関して意思決定ができる能力をいう。
(注9)慣れ親しんだ日常生活に関する事項(見たいテレビ番組やその日の献立等)に関する意思決定はできるが、本人に関する重要な決定への合意等(ケアプランの作成への参加、治療方針への合意等)には、支援等を必要とすることをいう。

なるほど、必ずしも介護保険制度の要介護状態に該当している必要はないのですね。

そうですね。従業員の申し出に基づき、家族の状態を確認することになります。

会社は、常時介護を必要とする状態に該当しているかを確認するために、要介護状態にあること等を証明する書類の提出を求めても問題ないのでしょうか?

書類の提出を求めることは問題ありません。ただ、介護保険制度の要介護状態区分において要介護2以上である場合に限られませんし、公的書類や医師の診断書等が提出できるとは限りません。したがって、申し出に医師の診断書の添付を義務づけることなどは望ましくなく、書類が提出されないことをもって介護休業を取得させないことはできません。また、この「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」の前提には、「この基準に厳密に従うことにとらわれて労働者の介護休業の取得が制限されてしまわないように、介護をしている労働者の個々の事情にあわせて、なるべく労働者が仕事と介護を両立できるよう、事業主は柔軟に運用することが望まれます」ということがあります。つまり、仕事と介護の両立支援の観点からなるべく介護休業の取得を拒まないようにという考えが示されています。

なるほど。今回、従業員から初めて介護休業を取得したいという相談がありましたが、今後もこのような相談が出てくるように思います。その時に対応できるように、介護休業や介護休暇の制度などについて復習してみます。
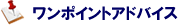
改正育児・介護休業法が2025年4月と10月に施行されますが、2025年4月から施行される項目のひとつに、介護離職防止のための取り組みがあります。この取り組みには、雇用環境整備と個別の周知・意向確認等の2つがありますが、今回の判断基準については、従業員から相談があったときの回答や情報提供の資料内容にも関わってきます。従業員向けの資料を準備されている場合は、最新情報を反映しましょう。
■参考リンク
厚生労働省「育児・介護休業法について」
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。